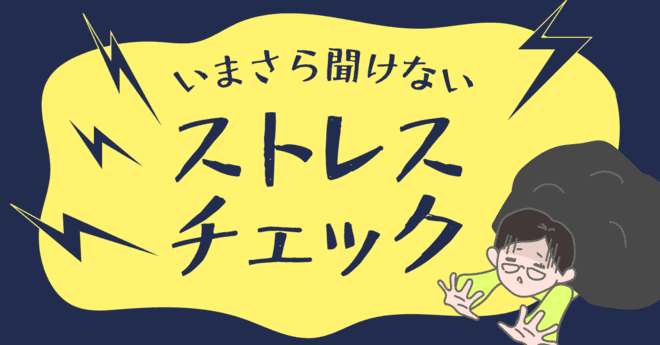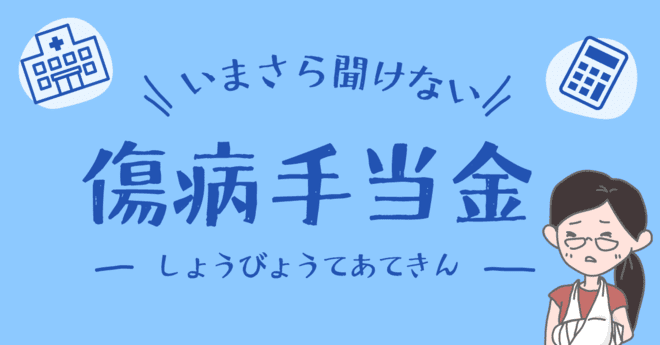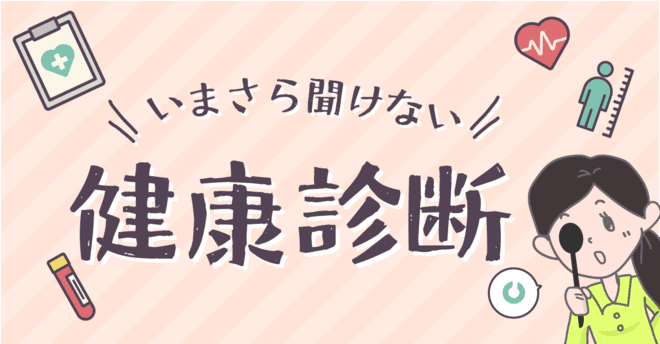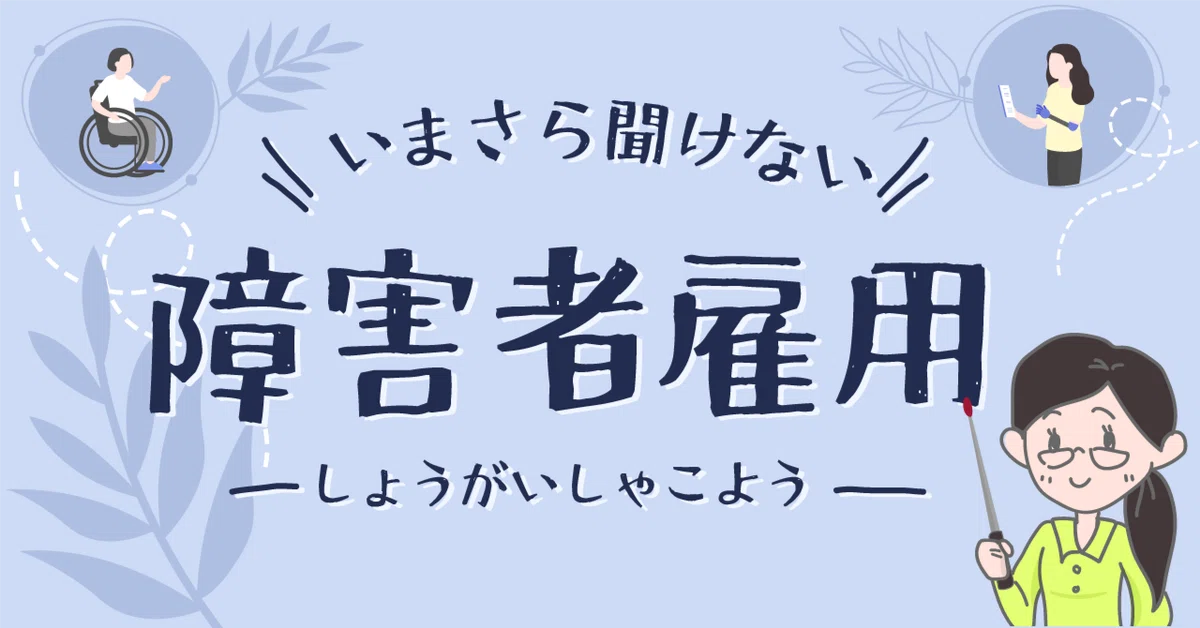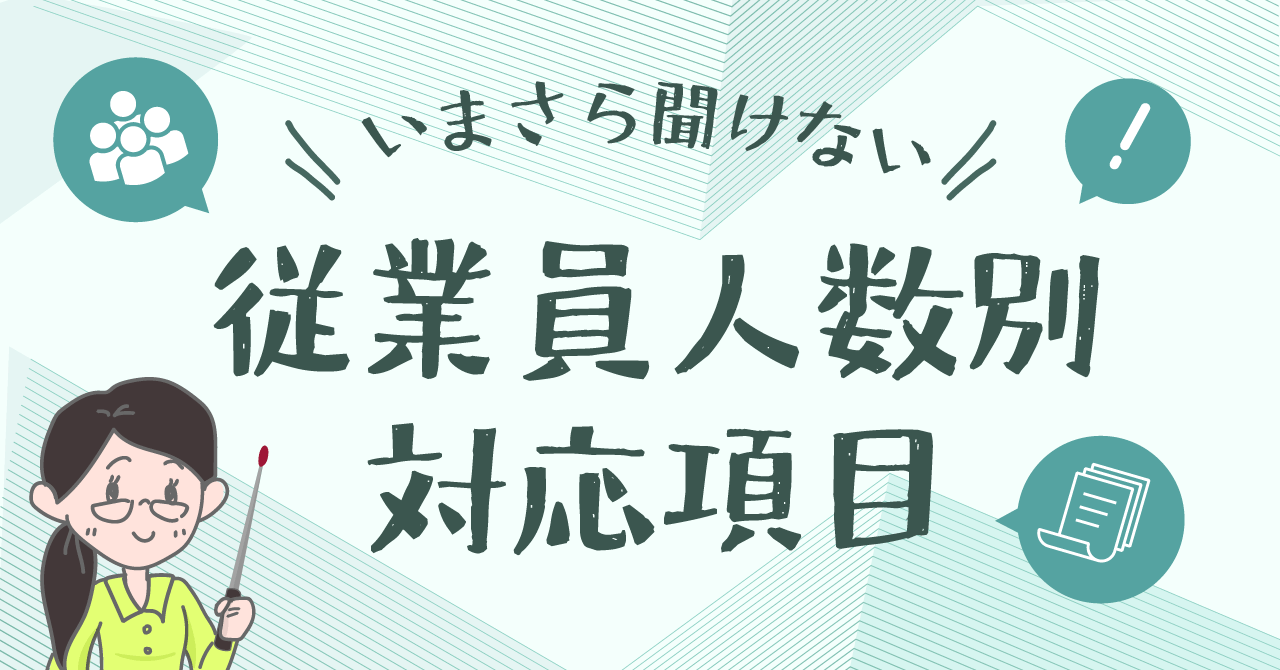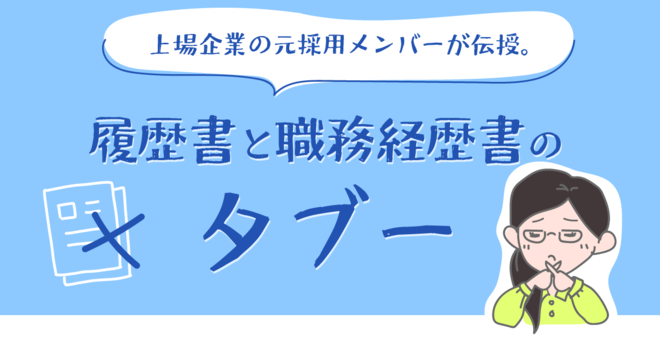みなさま、こんにちは。齊藤です。
今回のテーマは、
「ストレスチェック」についてです。
今回も、人事担当として必ず確認しておきたい事項の一つです。
弊社の労務に詳しいスタッフに聞いてきました。
早速まとめていきたいと思います!
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、従業員のストレスの程度を把握し、
従業員自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めるものです。
メンタルヘルス対策の一つでもあります。
従業員がメンタルヘルス不調となることを
未然に防止する一次予防を主な目的としています。
ストレスチェックが義務化された背景
ここ数年の精神障害による労災補償請求件数が増加したことがあります。
厚生労働省が公表している”過労死等の労災補填状況”を見てみると、
脳や心臓疾患による請求件数ならびに精神障害よる請求件数も増えています。
このような労災補償請求件数の増加から見てとれるように、
職場でのストレスが原因で起こるメンタルヘルス不調は、とても深刻な問題で
会社が早急に改善するべき課題といえます。
実施・報告の義務
労働者数が50人以上の事業場では、毎年(1年に1回)、
従業員に対してストレスチェックを実施する義務が課せられています。
50人未満の事業場については、努力義務とされていますが、
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいでしょう。
また、実施後は、その結果を遅滞なく労働基準監督署に報告する事も義務となっています。
衛生委員会での調査・審議
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、従業員、産業保健スタッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した上で、衛生委員会等の場を活用し、お互い協力・連携しつつ取り組むことが重要です。
このため、事業場におけるストレスチェックの実施体制、実施方法、情報取扱い等についてあらかじめ衛生委員会で調査審議・確認し、各事業場での取扱いを内部規定として策定、
従業員へ周知した上で、実施する必要があります。
ストレスチェック結果の分析と活用方法
ストレスチェックの結果は、
従業員のストレスの程度やその原因を理解するための重要な情報源です。
従業員は自らのストレス状況を知ることができ、セルフケアにつなげることができます。
会社は、個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計分析し、職場ごとのストレス状況を把握するとともに、
分析結果に応じて仕事量やサポート体制の見直しなど職場環境の改善に取り組むことが重要です。
また、ストレスの高い従業員に対しては、カウンセリングや場合によっては
休職などの対応を講じる必要があります。
なお、集団分析にあたっては、個人が特定されないよう10名以上の単位で集計する必要がありますので注意しましょう。
注意事項
ストレスチェック結果など個人情報は適切に管理し、従業委員のプライバシーに配慮しなければなりません。
そのため、実施者および実施事務従事者には守秘義務が課せられ、違反した場合は刑罰の対象となります。※Q&A参照
また、ストレスチェックを受けないことや、面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと、
高ストレスと評価された従業員が面接指導の申出を行わないことなどを理由として、不利益な取り扱いを行う事は法律で禁止されています。
Q&A
Q 労働者数50人以上の「労働者数」とは正社員のみですか?
A ストレスチェック実施における事業場の労働者数は、正社員、契約社員、
パートアルバイトなどの雇用従業員に加え、受け入ている派遣社員や出向者についてもカウント対象となります。
ただし、労働基準監督署への報告要旨の労働者数は、派遣社員の人数は除いて記載します。
Q 正社員が25名、アルバイトが10名、派遣会社から受け入れている派遣社員が20名という事業場なのですが、
ストレスチェックの実施義務はありますか?
A 正社員、アルバイト、派遣社員の合計が50名以上なので、ストレスチェック実施が必要な事業場となります。
なお、実施対象者は、正社員、アルバイトの35名となります。
Q 当社は派遣社員を受けいれていますが、派遣社員のストレスチェックは
派遣元(人材派遣会社)と派遣先である当社のどちらで実施するのですか?
A 派遣元(人材派遣会社)にて実施が必要になります。
ただし、集団分析を行う際には、派遣社員を含めて集団分析を行うことが望ましいとされています。
Q ストレスチェックの実施者はどんな人?
A 医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士または公認心理士に限られます。
Q ストレスチェックの実施事務従事者はどんな人?資格は必要ですか?
A ストレスチェック実施事務従事者は、会社の人事や総務担当者が担うこともありますが、特に資格は要しません。
ただし、実施事務従事者は、調査票の回収、データ入力、面接指導の勧奨などの実施者の補助を行い、記入された調査票などを見る機会がありますので、守秘義務が課せられます。(労働安全衛生法第105条)
また、従業員について解雇、昇進または異動に関して直接の権限をもつ監督的地位にある人(例えば人事部長や役員など)は、実施事務従事者になることができません。
Q 従業員にストレスチェック実施を強制できますか?
A 従業員に、ストレスチェックの実施を強制することはできません。
ただし、事業者、実施者、実施事務従事者は、ストレスチェックを実施していない従業員に対し、実施の勧奨をすることは問題ありません。
Q 従業員個人のストレスチェックの結果は会社が入手できますか?
A 結果は従業員個人にのみに直接通知されます。会社は本人が同意した場合に限り、個人の結果を入手することができます。
Q 従業員が、会社の指定した実施者でない「かかりつけ医」等で受検したいという場合、
ストレスチェックとみなして良いのでしょうか?
A 健康診断と異なり、ストレスチェックは、会社が指定した実施者以外で受ける手続きは規定されていません。
このため、会社が指定した実施者以外で受けた場合、ストレスチェックを受けたこととはなりません。
Q ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、それとも従業員にも負担させて良いのでしょうか。
A ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で会社にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、
当然、事業者が負担すべきものです。
Q 長期出張や長期の休職のために、ストレスチェックを受検できなかった従業員について、どのような対応が必要ですか。
A 業務上の都合や、やむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった従業員に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。長期の休職者については、
ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。
最後に
ストレスチェックは、従業員の健康保持のために欠かせないメンタルヘルス対策であることはもちろん、
会社にとってもメンタル不調による休職を未然に防げたり、
職場の問題点を把握できることにより職場改善に取り組め離職抑止や労働生産性の向上などが図れたり、
会社にとってもメリットがありますので、是非しっかりと行っていきたいですね。
いまさら聞けないシリーズはまだまだ続きます。
それでは、次回もまたお会いしましょう。
お楽しみに!
記事をシェアする
関連記事

いまさら聞けない『出生時育児休業(産後パパ育休)』
みなさま、こんにちは。齊藤です。今回のテーマは、出生時育児休業(産後パパ育休)です。事業務を行っていくうえで、必ずといっ…