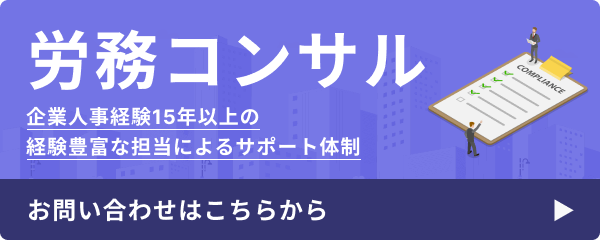みなさん、こんにちは!
HRマネジメント編集部です。
2025年4月に「育児・介護休業法」が改正されました。
これにより、企業には、柔軟な働き方を実現するための措置や雇用環境整備などが義務化され、従業員にとって、男女ともに仕事と育児・介護の両立がしやすい制度へと進化しました。
本記事では、人事・労務担当者はもちろん、これから育児休業・介護休業を検討している従業員にも役立つ
「最新の改正ポイントと実務での活用方法」をわかりやすく解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう~!
2022年の主な改正ポイント(おさらい)
• 父親も出生時育児休業(産後パパ育休)の新設により2回まで分割取得(合計4週間)可能に
• 夫婦で育休の交代取得など、柔軟な働き方の選択肢が増えた
• 就業時間のガイドライン明確化
└出生時育児休業中の就業は労使協定により可能となるが「週20時間以内」が上限目安
└長時間労働や深夜業務の回避が必要
→ 育児と両立できるよう、健康配慮が必要
【2025年4月】育児・介護休業法 改正ポイント
■育児休業改正
① 出生時育児休業分割取得の「申出期限」が緩和
改正前:2回目の分割取得でも 2週間前までに申請 が必要改正後:2回目は1週間前までに申請でOK!
→ 出産予定日のズレなどにも柔軟な対応が可能に。
ただし、通常の育児休業の場合は、育児休業の開始予定日の1ヶ月前までに会社に申出が必要。
② 出生時育児休業および育児休業について休業申出の撤回が柔軟に
改正前:原則撤回不可(やむを得ない事由が必要)
改正後:開始前(休業開始予定の前日まで)であれば撤回可能に!
→ 家庭の状況に合わせて柔軟に判断可能。
③-1 子の看護休暇の取得理由が拡大
改正前:子の看護休暇
改正後:子の看護等休暇
→これまでは病気・けが・予防接種・健康診断時に取得可能でしたが新しく入園(入学)式・卒園式・感染症に伴う学級閉鎖等が追加。
※休暇は無給でもOK。
ただし、出勤率に影響するため年次有給休暇付与日数の算出時には出勤扱いとしてカウントが必要。
③-2 子の看護休暇の対象となる子の範囲拡大
改正前:小学校就学の始期に達するまで
改正後:小学校第3学年修了(9歳に達する日以後の最初の3月31日)
③-3 労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
改正前:労使協定により継続雇用期間6か月未満の従業員は対象外
改正後:撤廃
→労使協定によって「継続雇用6ヶ月未満」の労働者を介護休暇の対象外にできましたが、この除外が廃止。
④ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
改正前:3歳未満の子を養育する従業員
改正後:小学校就学前の子を養育する従業員
→対象従業員が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、残業免除が必要。
⑤ 時短勤務制度の代替措置でテレワークを選択可能に
・3歳未満の子を養育する従業員に関しテレワークを選択できるように措置を講ずる事が事業主へ努力義務化。
■介護休業改正
① 介護休業制度の対象拡大(雇用要件の緩和)
改正前:労使協定により継続雇用期間6か月未満の従業員は対象外
改正後:撤廃
→従来、労使協定によって「継続雇用6ヶ月未満」の労働者を介護休暇の対象外にできたが、この除外が廃止。
→週2日以上の勤務があれば、勤続期間に関わらず介護休暇が取得可能に。
② テレワーク制度の整備
要介護状態の対象家族の介護にあたる従業員に関しテレワークを選択できるように措置を講ずる事が事業主へ努力義務化。
【2025年10月】育児・介護休業法 改正ポイント
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。
① 就業時刻等の変更
→所定労働時間は変えず、始業終業時刻をずらす。(始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる)
② テレワーク等(10日以上/月)
→週2回時間単位で取得可能。
→1日の所定労働時間を変更することなく利用することができ、始業の時刻から又は終業の時刻まで連続して時間単位で利用することができる内容とすること。
③ 保育施設の設置運営ベビーシッター補助制度
→ベビーシッターの手配および費用負担など。
④ 子の養育支援のための休暇
→年10日以上時間単位取得可。
※休暇は無給でもOK。ただし、出勤率に影響するため年次有給休暇付与日数の算出時には出勤扱いとしてカウントが必要。
⑤ 短時間勤務制度
→1日6時間勤務など、時短制度の導入。
→⑤を選択しなかったとしても、育児介護休業法により申し出があった場合には対応が必要。
2025年4月、10月の法改正により、入園(入学)式・卒園式など学校イベントに柔軟対応が可能になり、家庭イベントと仕事と育児の両立がしやすくなりました。
たとえば、「産後のサポートのために一時的に休みたいが、月1回の会議には出たい」「上の子の卒園式・入学式に合わせて柔軟に休みたい」といったニーズにも対応できます。
育児休業取得によって完全に仕事を休むのではなく、柔軟に調整・活用できるようになったのが、2025年改正の大きな魅力です。
よくある質問
【Q:男性の場合、育児休業は出産予定日前から取得できるの?】
→ 現行法上、男性には出産前の育児休業という制度は設けられていません。
しかし、企業によっては、配偶者の出産に際して独自の休暇制度を導入しているケースもあります。
【Q:実際の出産日が出産予定日より前後した場合、育児休業の適用期間はどのように調整されるの?】
→ 出産が予定より早く実現した場合は、その分だけ育児休業の開始日を前倒しで設定でき、逆に出産が遅れた際には開始日を後ろにずらすことが可能です。
変更がある場合には、育児休業の変更申請書を提出する必要がありますので、必要な手続きを事前に確認しておくことが大切です。
人事・労務担当者が準備すべき社内対応
① 法改正を盛り込んだ社内規程のアップデート
② 休業中の就業に関する同意書などの新設(※労使協定必要)
③ 健康確保と働き方配慮
④ 社内周知・研修
└管理職向け:対応マニュアルの配布
└社員向け:イントラネット、説明会、リーフレットでの周知
まとめ
育児・介護に関する制度が見直され、時短勤務やテレワーク、所定外労働の制限など、柔軟な働き方の選択肢が大きく広がりました。育児休業や子の看護休暇の対象が拡大されたほか、介護休業では継続勤務の要件が緩和されるなど、ライフステージに応じて無理なく働ける環境づくりが進められています。
企業側には、制度の見直しや従業員への周知、相談体制の整備などが求められます。制度を正しく理解し、社内規程や運用の見直しを進めることで、離職防止や働きやすい職場づくりにつながります。
以上、今回は最新の改正内容を含めた育児・介護休業法の改正ポイントについて、まとめてみました。
次回も、実務で役立つ情報をどんどん紹介していきますので、ぜひお楽しみに!
参考:厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」
参考:厚生労働省「令和 6年改正育児・介護休業法に関する Q&A」
参考:厚生労働省 「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正」
記事をシェアする
関連記事
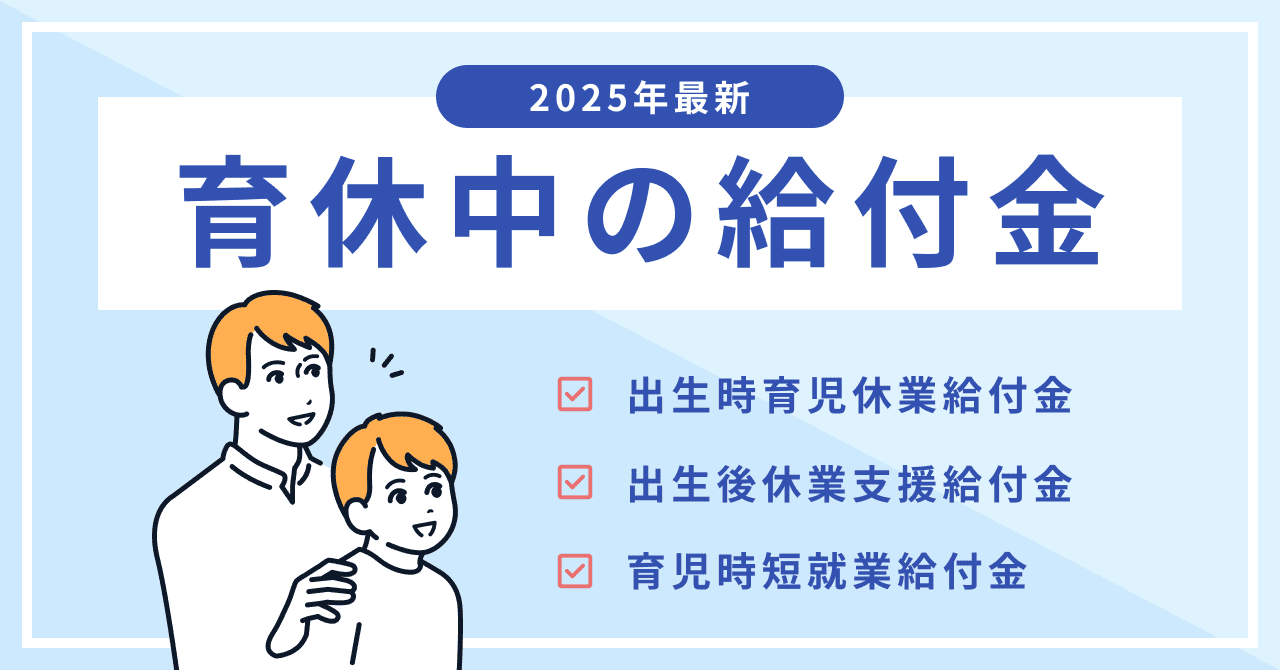
【2025年最新】「育休中の3つの給付金」
みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。 2025年4月の改正でさらに柔軟に取得しやすくなった出生時育児休業…
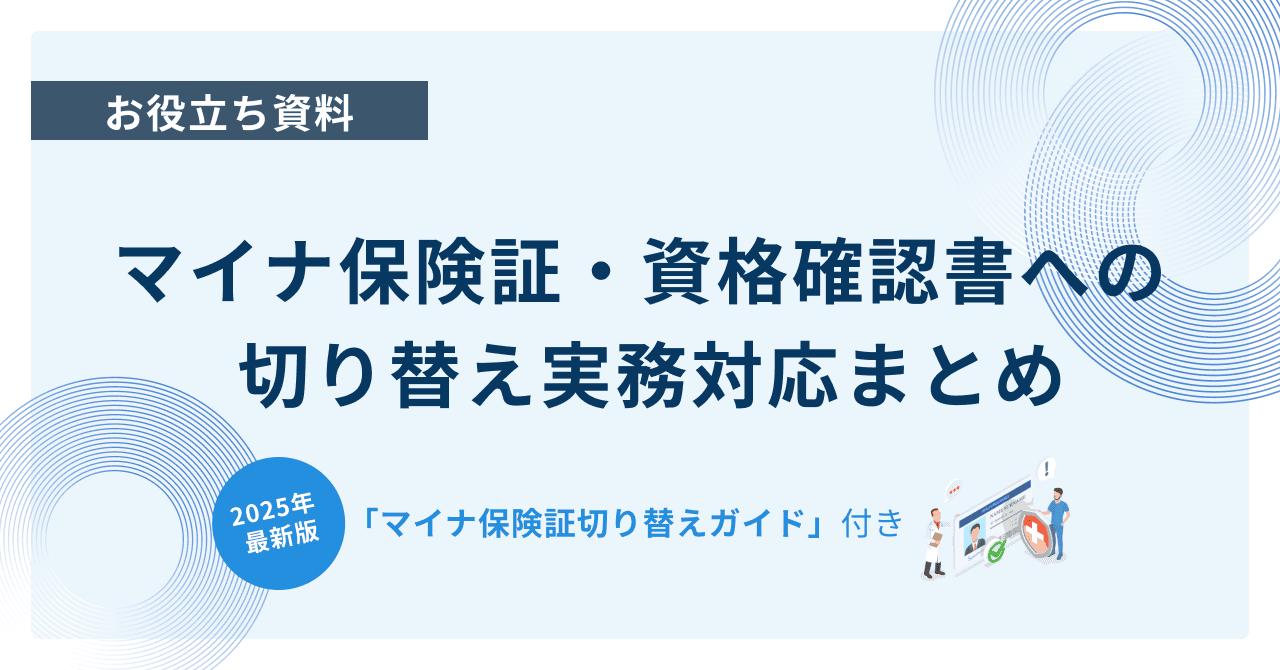
【完全ガイド】2025年12月で健康保険証が廃止|マイナ保険証・資格確認書への切り替え実務対応まとめ
みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。 政府方針に基づき、2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行…
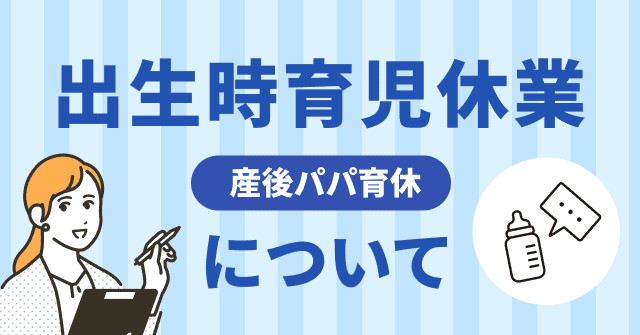
人気ランキング
-
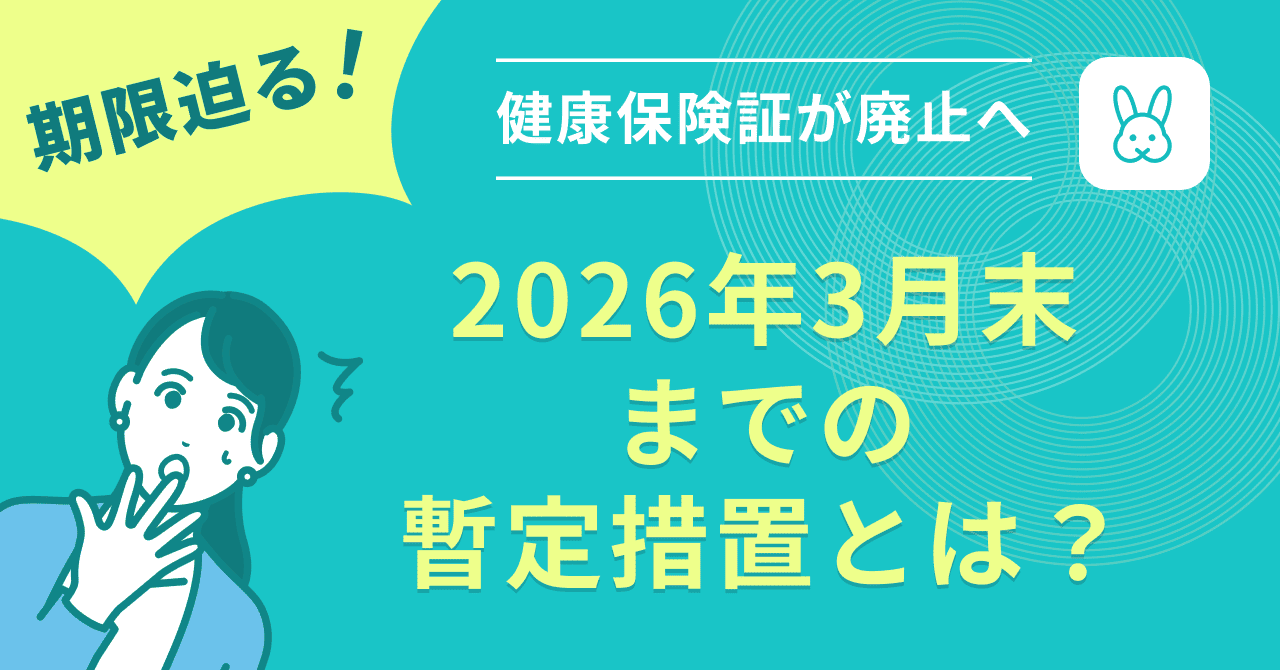 2025.11.28 お役立ち情報1
2025.11.28 お役立ち情報1期限迫る!健康保険証が廃止へマイナ保険証移行と「20…
-
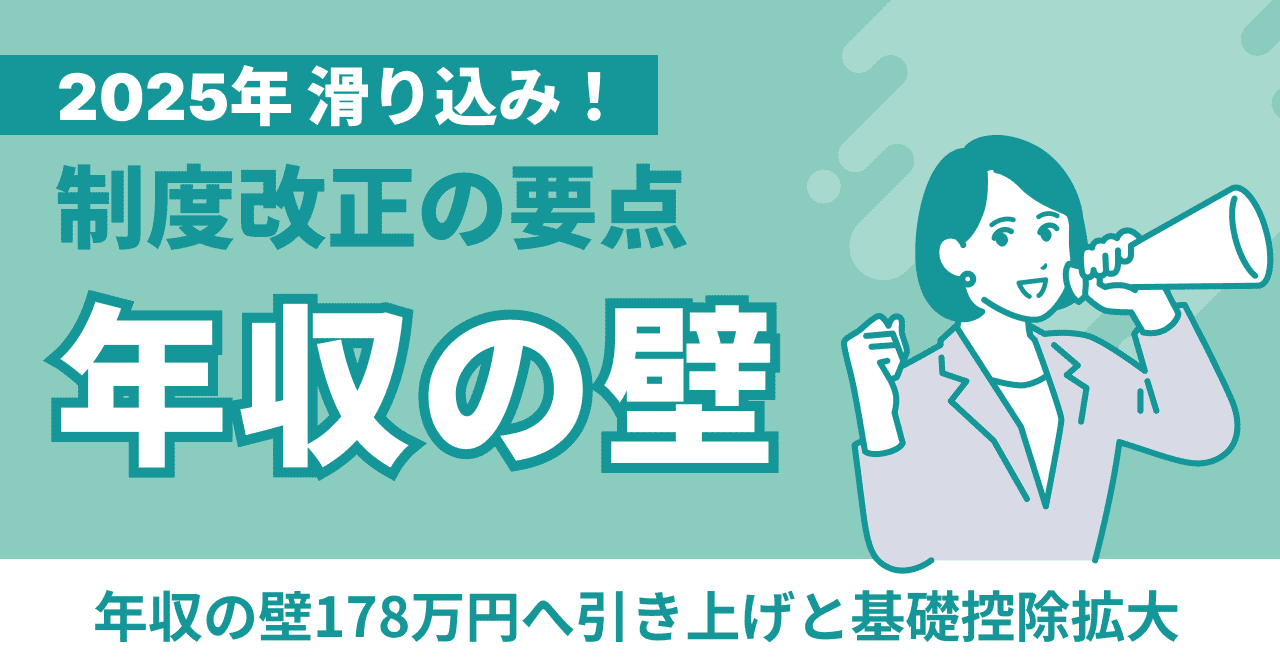 2025.12.19 人事実務ノウハウ2
2025.12.19 人事実務ノウハウ2制度改正の要点|「年収の壁」178万円へ、基礎控除拡…
-
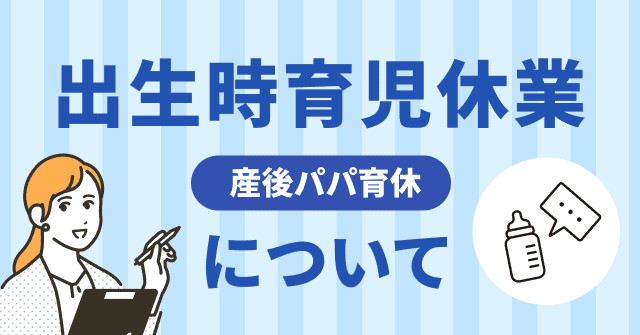 2026.1.29 人事実務ノウハウ3
2026.1.29 人事実務ノウハウ3【2026年完全版】いまさら聞けない『出生時育児休業…
-
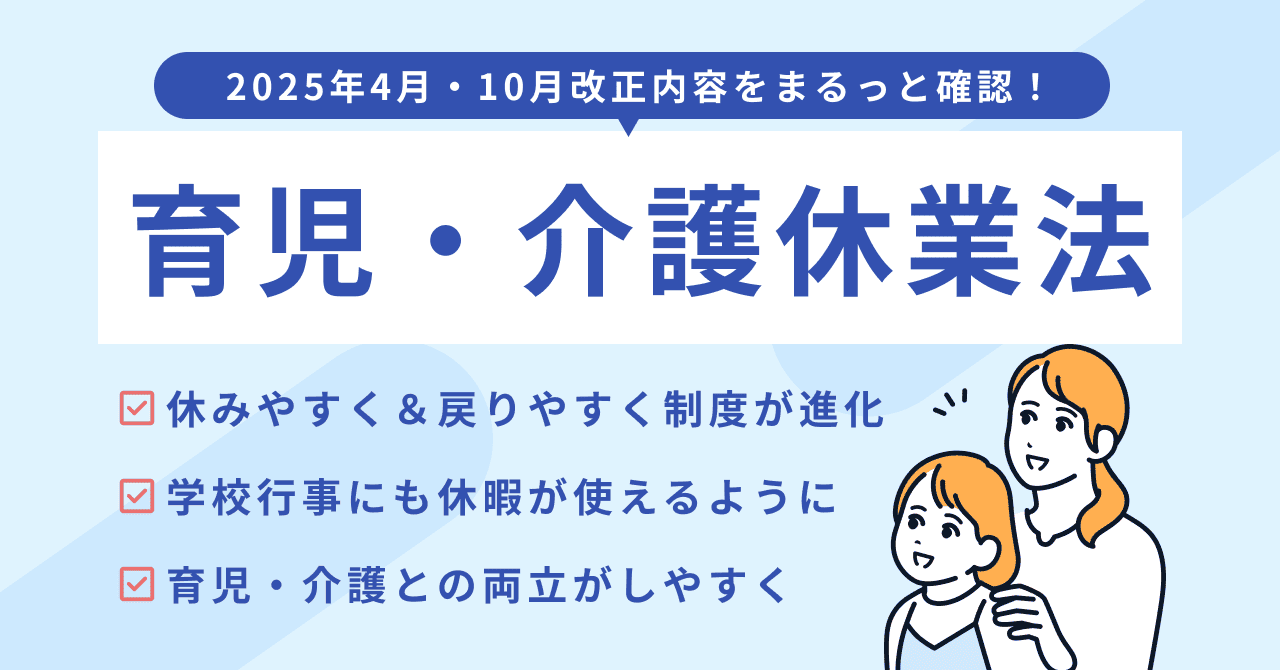 2025.8.8 人事実務ノウハウ4
2025.8.8 人事実務ノウハウ4最新版:【2025年4月・10月】育児・介護休業法の…
-
 2025.10.31 人事実務ノウハウ5
2025.10.31 人事実務ノウハウ5【最新版】年末調整・確定申告2025年~2026年版…