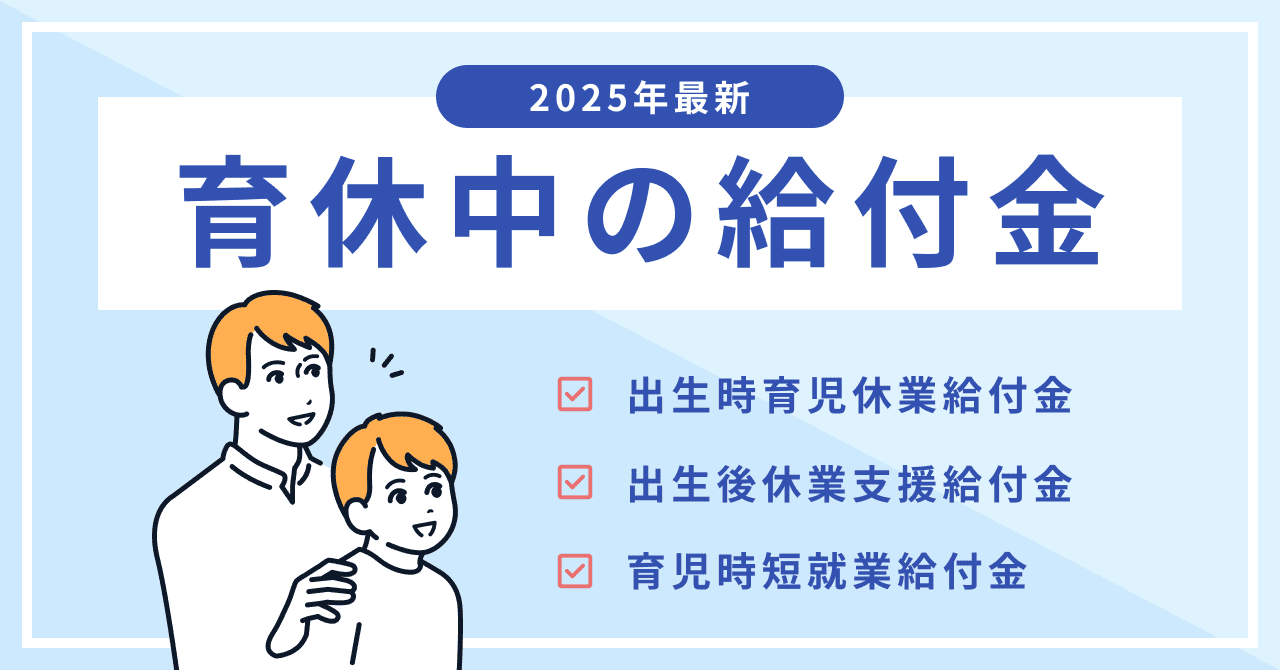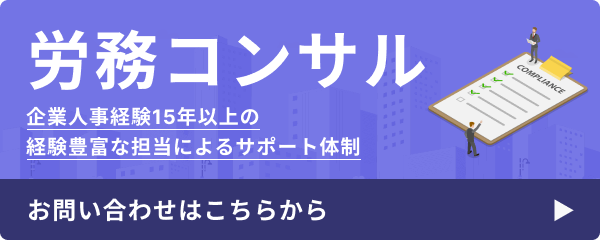みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。
2025年4月の改正でさらに柔軟に取得しやすくなった出生時育児休業(産後パパ育休)。
それにともない受け取れる出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金などの制度も、人事・労務担当、従業員ともに知っておきたい重要なポイントです!
さらに、職場復帰後も仕事と育児を両立しやすくする育児時短就業給付金という制度も始まり、制度活用の選択肢が広がっています。
この記事では、以下の3つの制度について、
人事・労務担当、従業員どちらにも役立つ視点でやさしく解説します。
・出生時育児休業給付金
・【新制度】出生後休業支援給付金
・【新制度】育児時短就業給付金
厚生労働省の最新情報をもとに、人事・労務担当の実務対応ポイント、従業員が得られるメリットなどをまとめました。
それでは、詳しく見ていきましょう~!
出生時育児休業制度とは?
子どもの出生後8週間以内に4週間まで育児休業(28日)を取得できる制度のことで、この期間に支給されるのが「出生時育児休業給付金」です。
支給要件を満たした場合に雇用保険から、支給されます。
ポイントまとめ
・最長4週間(28日)で、2回まで分割取得可能
・一定条件のもと、一部就労しながら取得可能
・給付金は非課税のため、手取りベースでの負担軽減効果あり
・社会保険料も免除対象(健康保険料、厚生年金保険)
【2025年4月創設】出生後休業支援給付金とは?
2025年4月に新たにスタートした「出生後休業支援給付金」は、共働き・共育てを推進するために創設された新制度です。
支給対象と要件
子の出生後、育児休業を合計14日以上取得している被保険者
(または父親の場合など、特定事情がある場合は条件が緩和される)が対象です。
※配偶者にも一定の育児休業取得要件がある場合があり、家庭の事情により例外措置が設けられています。
支給内容
休業開始時の賃金日額×休業日数(上限28日)×13%で算出されます。
※他の育児休業給付金と合わせた申請となり、具体的な支給期間は産後休業の有無など状況により異なります。
【2025年4月創設】育児時短就業給付金とは?
2025年4月に新たにスタートした「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを育てながら短時間勤務をする方に向けた新制度です。
支給対象と要件
雇用保険の被保険者で、2歳未満のお子さんを養育するために、勤務時間を短縮して働く場合が対象です。
被保険者期間や、対象月ごとの就業状態(所定労働時間の短縮、他休業給付の非同時受給など)の条件を満たす必要があります。
支給内容
時短就業中の賃金額の10%が支給されますが、支給開始時の賃金水準との比較により調整され、設定した上限内で算出されます。
一定の条件(賃金低下がない、上限超過、最低限度額未満など)では支給対象外となります。
人事・労務担当が押さえるべき実務ポイント
①社会保険料免除の対応
②一部就労がある場合は労働日数・時間の管理が必須
③対象期間の正確な把握と、人事・給与部門との連携
④給付金申請のサポート
⑤給付金は会社経由で申請
⑥従業員への支給時期・見込み額の事前案内が必要
従業員が知っておきたい制度の使い方
①育休中の家計もサポート
②育休中は給与ゼロでも、給付金+社会保険料免除で負担軽減
③「出生後休業支援給付金」により、育休中の手取りが実質ほぼ10割に
④申出は早めに!会社との相談がカギ
⑤育休の申出は原則1か月前まで(例外あり)
※出生時育児休業は2週間前までの申出
⑥一部就労・時短勤務希望の場合は、早めに人事・労務部門へ相談を
よくあるQ&A
【Q:出生時育児休業(産後パパ育休)と通常の育休は併用できる?】
→ 出生時育児休業のあとに通常の育児休業を取得することが可能です。両方とも給付金と保険料免除の対象です。
【Q:パート・契約社員でも給付金を利用できる?】
→ 雇用保険に加入している方であれば、パート・契約社員も対象です。
※要件を満たした場合
【Q:育児時短就業給付金はいつからもらえる?】
→ 育休復職後、時短勤務を開始して賃金が下がった月から支給対象になります。
※申請は会社経由
【Q:育児時短就業給付金と育児休業給付金は両方もらえる?】
→ 両方を同時に受給することはできませんが、時期をずらして受け取ることは可能です。
たとえば、育児休業給付金を受給した後に復職し、短時間勤務を開始した場合、育児時短就業給付金の対象となることがあります。
人事・労務担当者が準備すべき社内対応
① 法改正を盛り込んだ社内規程のアップデート
② 休業中の就業に関する同意書などの新設(※労使協定必要)
③ 健康確保と働き方配慮
④ 社内周知・研修
└管理職向け:対応マニュアルの配布
└社員向け:イントラネット、説明会、リーフレットでの周知
まとめ
出生時育児休業給付金、育児休業中の社会保険料免除、育児時短就業給付金は、
働きながら育児をする従業員にとってメリットの大きい制度です。
制度改正により利用しやすくなった一方で、正確な情報把握と適切な申請管理が求められます。
人事・労務担当は実務フローや申出制度の整備を、従業員は制度の特徴や条件を理解したうえで、
安心して制度を活用していきましょう。
参考:厚生労働省「育児休業等給付について」
参考:厚生労働省「「出生後休業支援給付金 」を創設します」
参考:厚生労働省「「育児時短就業給付金」を創設します」
記事をシェアする
関連記事
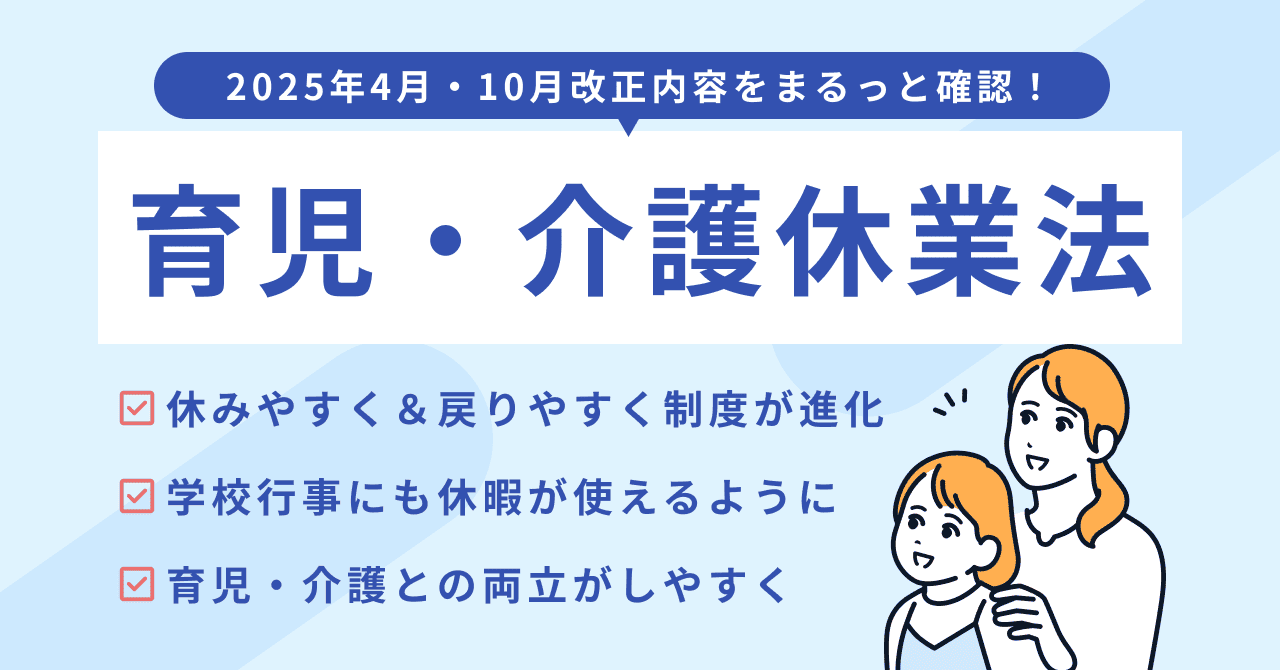
最新版:【2025年4月・10月】育児・介護休業法の改正ポイント
みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。 2025年4月に「育児・介護休業法」が改正されました。これにより、…
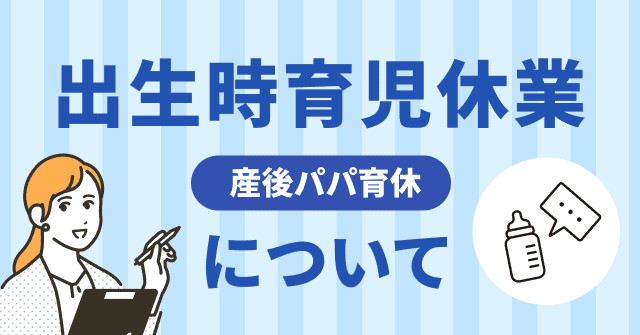
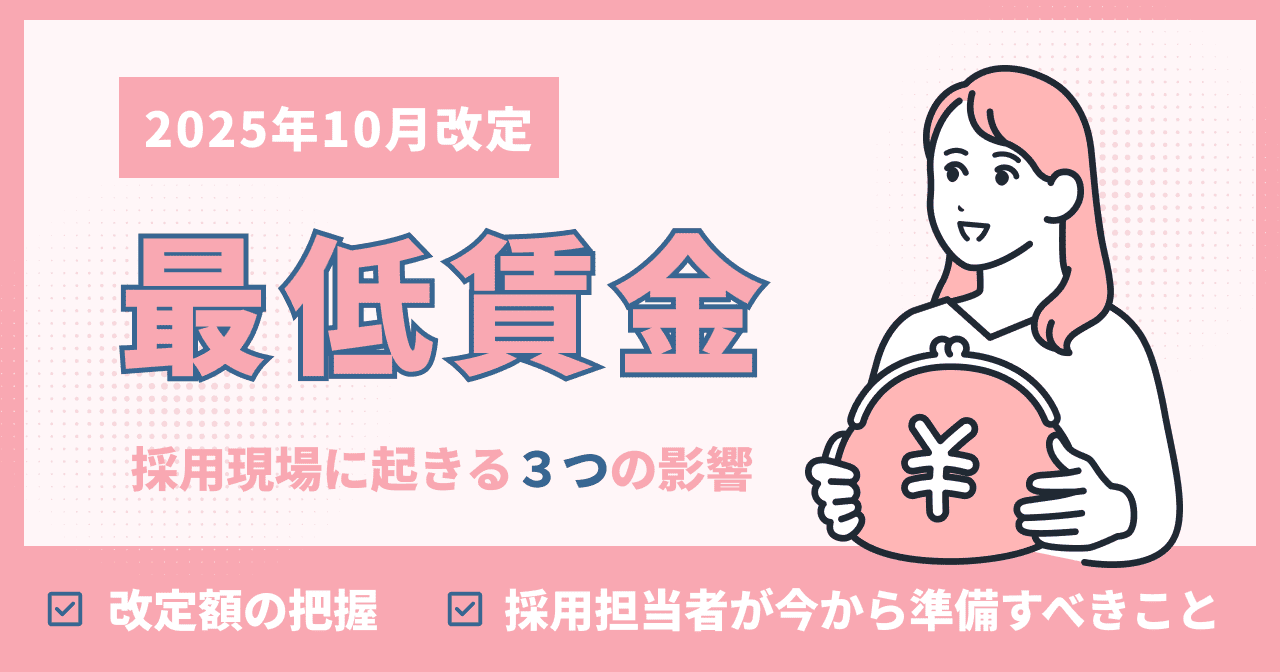
【2025年10月最低賃金改定】採用現場に起きる3つの影響
こんにちは!HRマネジメント編集部です。今回は、2025年の最低賃金の改定について、お届けいたします。 2025年10…
人気ランキング
-
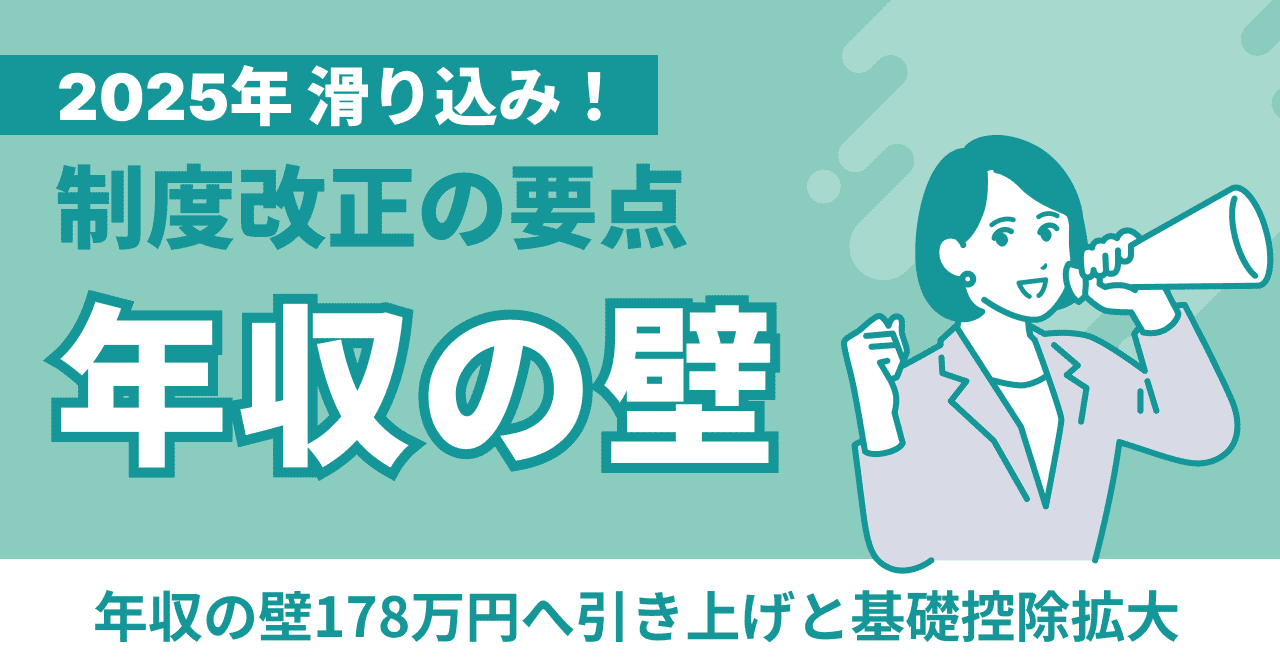 2025.12.19 人事実務ノウハウ1
2025.12.19 人事実務ノウハウ1制度改正の要点|「年収の壁」178万円へ、基礎控除拡…
-
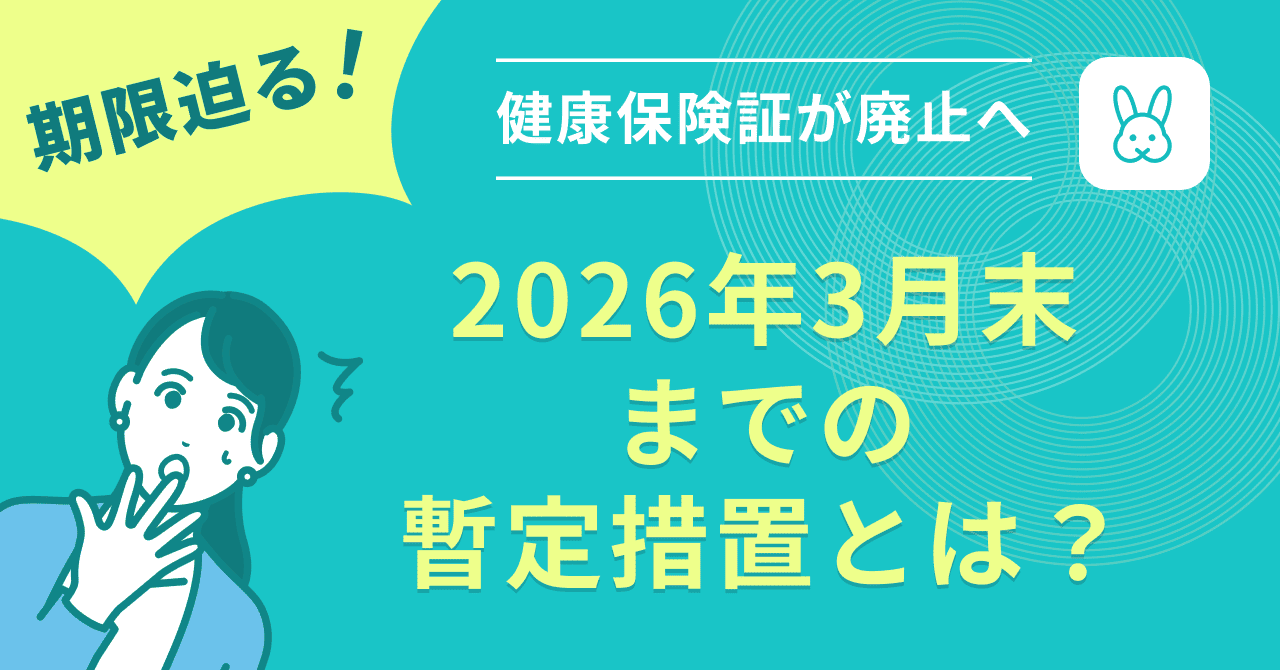 2025.11.28 お役立ち情報2
2025.11.28 お役立ち情報2期限迫る!健康保険証が廃止へマイナ保険証移行と「20…
-
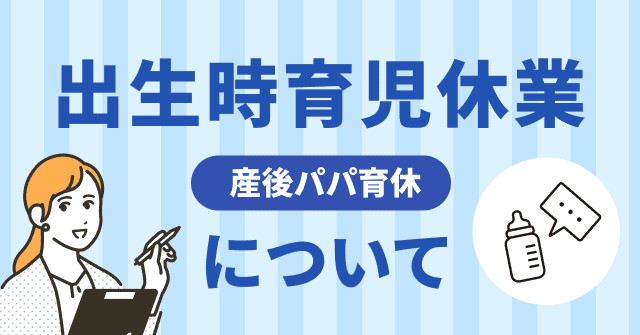 2026.1.7 人事実務ノウハウ3
2026.1.7 人事実務ノウハウ3【2026年完全版】いまさら聞けない『出生時育児休業…
-
 2025.12.5 お役立ち情報4
2025.12.5 お役立ち情報4ふるさと納税今年もギリギリで…!ワンストップ特例制度…
-
 2025.10.31 人事実務ノウハウ5
2025.10.31 人事実務ノウハウ5【最新版】年末調整・確定申告2025年~2026年版…